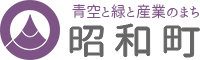本文
保険税の算定方法
保険税は病院などへの医療費の支払のほか、高額療養費などの給付費、出産育児一時金、葬祭費等、国民健康保険事業の安定運営に欠かせない重要な財源です。納期限までに必ず納付してください。
| 項目 | 課税対象額 | 医療分 | 後期高齢者支援分 | 介護分 |
|---|---|---|---|---|
| 全ての国保加入者 | 40〜64歳の加入者 | |||
| 所得割額 | 前年の総所得から 43万円※1を控除した額 |
7.90% | 2.92% | 2.43% |
| 資産割額 | 現年度の固定資産税額 | 0% | 0% | 0% |
| 均等割額 | 加入者1人あたり | 28,000円 | 9,700円 | 9,500円 |
| 平等割額 | 1世帯あたり | 27,500円 | 8,500円 | 7,000円 |
| 年税額 A+B+C |
A |
B (限度額 240,000円) |
C (限度額 170,000円) |
|
※1 合計所得金額が2,400万円以下の場合。2,400万円超2,450万円以下の場合は29万円、2,450万円超2,500万円以下の場合は15万円が、それぞれ控除されます。2,500万円超の場合は、控除額は0円となります。
- 上記の税率で算定された年税額を12期に分けて納付していただきます。年度途中に資格を取得、喪失した場合は年税額を月割計算します(健康保険料は月末日に資格を有していた保険者へ納めることになっています)。
- 1期~3期(4月~6月支払期)は仮算定月です。前々年の所得から仮徴収の税額を算定し、賦課します。仮算定期間は原則として税額変更できません。
- 4~12期(7月~翌年3月支払期)は本算定月です。7月になると、前年1月1日~12月31日の所得を基に、年税額を決定・通知します。算定された年税額から、仮算定として賦課されていた金額を差し引き、分配することで本算定の1回あたりの納付額が決まります。
- その世帯の国保加入者全員が65歳以上74歳以下の年金受給者(年間18万円以上)で、国保税と介護保険料を合計した金額が年金の受給額の2分の1を超えない方につきましては、年金からの天引き(年金特別徴収)が行われます。
また、申請をしていただくことにより、年金からの天引きではなく、口座振替にてお支払いいただくことができます。
国民健康保険税の軽減について
軽減になるかの判定をおこなう際の前年中の世帯の合計所得を「軽減判定所得」といいます。この軽減判定所得が一定基準以下の場合に、均等割額と平等割額が軽減されます。ただし、所得申告をしていないと適用されません。
軽減判定所得
- 国保に加入していない世帯主(擬制世帯主)の所得も含みます
- 65歳以上の年金所得者は、所得から15万円を控除します
- 専従者給与は所得の対象になりません
- 専従者控除は適用されず、事業主の事業所得に含みます
- 7割軽減
軽減判定所得が43万円+10万円×(給与所得者等※2の数-1)以下の世帯 - 5割軽減
軽減判定所得が43万円+{29万5千円×被保険者数}+10万円×(給与所得者等※2の数-1)以下の世帯 - 2割軽減
軽減判定所得が43万円+{54万5千円×被保険者数}+10万円×(給与所得者等※2の数-1)以下の世帯
※2 「給与所得者等」とは、一定の給与所得者(給与収入金額が55万円を超える方)と公的年金等の支給を受ける方(公的年金等の収入金額が60万円を超える方(65歳未満)または125万円を超える方(65歳以上))を指します。